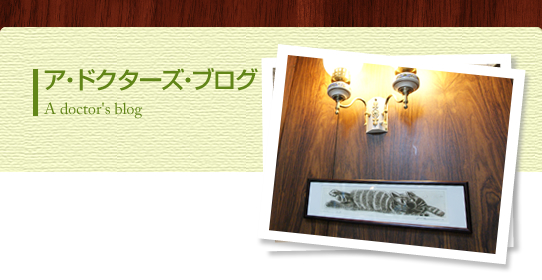2025年2月28日 (金) 09:18
ジェシー・アイゼンバーグ監督 A24 U-NEXT
2025年公開映画/2025年に観た映画 目標52/120 5/16
あまりにリアル・ペインが良かったので。初監督作品も観て見ようと。そしたら配給はA24、なんかもう、成功してる感じですよ、最初からこの扱いか、天才っていうか努力の人なんでしょうけれど、才能が凄い。五百億分の一でいいから分けて欲しい・・・息をしているだけで何も産み出せず、馬齢を重ね、以下略。
ネットの中でライブが行われているような空間で歌い出すジギー(フィン・ウォルフハード)、場面変わって女性の為のセーフハウスを運営しているエブリン(ジュリアン・ムーア)は親子で・・・というのが冒頭です。
これが初監督作品!!!ジュリアン・ムーア出てるし、フィン・ウォルフハードも出てるよ!
で、親子関係映画だったか・・・しかも母親と息子の話しでした。ここはあまり好みでは無いのですが、作品はなかなか良かったです。でも邦題はどうなんだろう・・・興味を削がれる感覚しか無いし、雑。直訳もちょっと意味が分からないけれど、常套句なんでしょうか?慣用句で意味が違うのかも。
いつも通り、ジュリアン・ムーアって嫌な時の顔とか、じわじわと理解し合える時の表情の演技上手い、と思ますし、流石。
息子の、どうしようもなさ、というか無力感やダメな部分は、年齢的にも仕方ないし、まぁ少しダメの度合い、この年代で、それは無いのでは?というイタさも感じられます。政治的な意味に無頓着だし鈍感過ぎるし、自分の名前のイニシャルの付いた帽子をかぶるのも、なんでも自分のサイトの話しになってしまうのも、子供なんだからある意味仕方ないし、こういう扱いを受けないと、男性としては成長出来ないので仕方ない。我慢して気付くしか無い。そしてアメリカでも、男子と女子の精神年齢には開きがある事が分かったけれど、まぁ全世界共通的な部分でもあるでしょうね。
それと対比される母親のダメさは、ちょっと引いてしまうくらい根深い・・・この差を埋められない感覚が、個人的な感覚なんだけれどあって、それがやはりオトナとして嫌なんだけれど、きっと私も若い世代から行動を観察されているとあるんでしょうね・・・気づけないのは致命的で改善の可能性がゼロだという事を指し示していて、非常に恐ろしさを感じます。
結構な嘘もつくし、その小狡さ、が鼻につく。そして客観視すると、エレベーターが来る前に話しかけただけで解雇を言い渡される可能性感じているという権力勾配に無頓着な所が息子であるジギーにも似ていて、家族の恐ろしさ、遺伝子的に逃れられないのが本当に恐ろしい。
しかも、よく考えるとこのエレベーター前で話しかける女性に対する扱いの酷さ、この後とある人物の前ではようはダシに使われ、容姿を(コスチュームだけど)馬鹿にされ、あまつさえ、夫と息子に対する嘘に再利用されてる・・・
それとこの映画の話しで身につまされるのは夫。この夫の扱われ方、それも家族からの扱われ方。そしてその対処方法の真っ当さと相まって、非常に爪痕残してくる。
これだとシングルの方がまだマシなのかも知れない、と思わせる存在でなかなか。
音楽の使い方、特にいろいろな上手さがあるのですが、曲の頭の部分を何度も聞いていて、それがある変化が起こるラストの感覚、新鮮でした。
ジェシー・アイゼンバーグが気になる方にオススメします。
2025年1月28日 (火) 09:14
クリント・イーストウッド監督 ワーナーブラザーズ U-NEXT
2025年公開映画/2025年に観た映画 目標52/120 2/8
「陪審員2番」があまりに面白かったので、ついイーストウッドの個人的ベストを確かめたくなって、おそらく10回目くらいの試聴です。ですが、何度見ても素晴らしい作品。
畑を耕す一家の周囲に砂埃が舞い、嵐が訪れようとしています、そこにオンボロな車がやって来て・・・というのが冒頭です。
イーストウッドは落ちぶれたドサ回りをしている売れない歌手レッド・ストーバルで、姉の家に寄ったところで、甥のホイットとお爺さんと一緒にナッシュビルで開かれるグランド・オープリーというオーディションを受けるために旅に出ます。甥のホイットを演じているのは実の息子のカイル・イーストウッド、後のプロの音楽家でベーシストです。しかもイーストウッドの「ルーキー」とか「グラントリノ」の映画の音楽も担当しています。
イーストウッド作品は基本的にマッチョで漢汁溢れる映画がほとんどなんですけれど、この作品と、おそらくもう1つ「ブロンコ・ビリー」でだけ、違ったキャラクターを演じています。
それは負けを認める、夢破れる、世界の認識を自分で変える、という誰にとっても当たり前で歳を取ったり病気になったり精神的に落ち込めば誰にも必ず訪れる、その負を受け入れる男を描いていますし、すごく数少ないイーストウッドが、◯〇する映画です、一応伏せます。普通の多くのイーストウッド映画では描かれない場面です。ほとんどの映画でイーストウッドは負けないし、勝ち気で強気でヒーローです。だからこそ人気があるのもわかりますけれど、ずっと勝ち続ける、というのは無理な話しです。そして、正義のヒーローですら正義と自身の行動の葛藤が起こる世界の中で、イーストウッド的な男気はある種の狂気すら孕んでいると思いますが、それがほとんど無い、稀有なイーストウッド作品です。
この映画はリリシズムを描いていますし、ある種のノスタルジーでもあるし、自己憐憫という部分もあるでしょう。しかし、それ以上の事が起こっていると思います。
ある種のアメリカンドリームの終焉でもあります。
曲も大好き。
しかし邦題は本当に嫌ですね・・・
2024年9月20日 (金) 08:57
セリーン・ソン監督 A24 U-NEXT
2024年公開映画/2024年に観た映画 目標 36/100です。 現在は27/88
まだU-NEXTさんの消費しなければいけないポイントがあったので。
かなり評判が良かったですし。PAST LIVESという単語にも興味あります、過去に生きてる、と捉えてしまったので。
深夜4時のバーカウンターで座る、アジア系の男女と白人男性をカウンター越しに見ていると思われる英語圏の話し声で、どういう3人組なのか?想像している会話が聞こえていて・・・というのが冒頭です。
ラブロマンスものって基本的に興味が無いのですが、過去に生きる、という事には興味があります。誰しもそういう部分があると思うのです。そして女性よりは男性はロマンティックな生き物。というか、恐らくそういう風に育てられてもいます。文化圏は違っても、恐らく全世界的には、男性が生きやすいように設計されているとも言えますので、夢を見ていられる。
とは言え、この映画の状況はかなり特殊ですし、まぁ主人公に感情移入して見ているのであれば、大変心地よい映画体験とも言えます。
会話劇です。かなりビターと言えなくもないけれど、それだけじゃなく、文化圏の違いも扱っていると思います。
で、ロマンティシズムに満ちているとは思いますけれど、何と言いますか、昨今のこの手のロマン的な映画に詳しくないですし、こういう場合は男女を逆転させても成立するか?を考えてしまいます。でもそれはネタバレになるので、後述として、映画そのもの、俳優の演技含めて、悪くなかったです。
私は男性の精神年齢はマイナス20歳だと思っているのですが(特にうちの国は)、この映画の中でもそんな感じです。
12歳で移住してから会っていない男女が、12年後の24歳時にSNSでテレビ電話(という表現が古くてすみません、スカイプとかいうのが正しいのでしょうか?)で再会するも、NYとソウルに離れていることが分かり・・・の後はネタバレに繋がりかねないので、ご想像にお任せしますけれど、そういう話しです。
私は男性なので、どちらかと言えば、男性の感情は分かる気がしました。逆に女性の人の考えがあまり理解出来ませんでしたし、最後の最期の行動は謎。なんでそれ???ってなりました・・・
ロマンス要素だけを求める人には向かない作品とも言えるので、現実をそれなりに楽しめている人に、大人の人に、オススメ致します。
アテンション・プリーズ!
ここからはネタバレありの感想です。未見の方はご注意下さい。
とは言えまぁネタバレがこの映画にはあまり問題ない作品ではあると思いますが・・・
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
ネタバレありとして、まず、この女性ノラは何を求めているのか?という事ですね。まず、カナダへの移住を求めていたわけではない。それは親の都合です。
ですが、NYへは移住している。しかし、カナダからNYへの移住も困難でしょうけれど、ソウルからNYへの移住は難しさが段違いな様に見えますし感じます。そして、NYで生きてる私、つまり自分の尊厳の一部になっている気がします。もちろん凄い事ですし、上昇志向の強い人間は、何時かはソウルから、もっと言えば儒教的な世界や男尊女卑文化から距離を取ろうとしたでしょう。ですが、それでも、ヘソンがNYへ行く事のハードルの高さは、なかなかだと思いますね。
決して上昇志向が悪いわけではありませんけれど、ノラも旦那に言っているように、ヘソンが男性主義社会のソウルで生きてて、だから凄くコリアンに感じる、と言ってますけれど、それはある種当然で、ヘソンもノラにニューヨーカーを感じたでしょう。お互い様なんだけれど、上昇志向とか、私という主導に合わせろ、という感覚を感じるのです。それは、実は凄く男尊女卑社会の男性社会で観られる権威主義的。ヒエラルキーを敏感に感じ取って、その中での礼節を重んじる、なんなら忖度する。
ヘソンの一人っ子で収入の面で結婚出来ない事に対しても、割合自分の感覚だけで、結婚した方が良い、という発言があり、まぁマウントに、見ようと思えば見える。またそれ以上に、自分の環境に、無自覚とも言える。結婚しない自由もあるし、ここはニューヨーカーとは思えぬ発言で、同じニューヨーカーにはこんな事言わないはず。つまり、です。親しみもあるけれど、心の奥底で、イケテる進んでる自分と、ソウルというかつて自分も居たが遅れた田舎から来た男、という図式をノラの頭の中で捉えている振る舞いに、感じるのです。
ソウルが恋しいけれど、そこが嫌なら出て行けばよいし、なんでNYの私の所に会いに来てくれないの?という主張が強いのも、上昇志向の強い人に(男女関係なく)よく見られる傾向な気がします。
そもそもノラは訪ねられて、迎えてるわけで、ヘソンとの友情を感じていても、愛情は既に醒めていると思われます。
で、ココで個人的にイヤだな、と思うのが、男女逆だった場合、何となく、後ろめたいなら隠すような気がします。オープンにしているようで、夫やヘソンという 選べる立場 を楽しんでいるように見える、という事です。
難しいのは夫の方で、非常に好感持てる感じです。言い分も分かるし、卑屈な感覚に、普通なります。そこで卑屈になり過ぎずに、相手を気遣う。イイ人。
もし、男女が逆で、NYに居る男の妻と一緒に、ソウルから女性が訪ねてきたら、一緒に食事するでしょうか?なんとなく、しない方が礼儀で、それはそれ、これはこれ、な気がします。それに遭わせたら会わせたで、嫉妬心や逆に自分を尊重して見せるようなわざとらしいマウンティングをしてきそうです。それか、後で不機嫌になり、何年たってもこの同じネタで不機嫌の際には必ずこの話題を出されて、赦しを乞うても、次の怒りの際には忘れて同じテンションで怒り出す事でしょう。そんなポイント貯めない方が良いに決まってるし、既婚者の人々がこういう問題をどのように解決しているのか?全く不明です。何年たっても新鮮に怒れる人が、私の考える女性の恐ろしい所ですし、全然全然全然全然理解出来ませんし、別の生き物だとも思います。
まぁ言うても、ヘソンだって踏ん切りをつける為に来ているのは、まぁ間違いないですし、なんなら少しくらいは何かあってもいいかも、は思っててもオカシクナイです、男性ってそういう生き物ですし。でも、結局彼は強引な事は何もしない紳士的な男で、優柔不断に見えても、道を踏み外さない男。それだけで男尊女卑社会でソウル社会の中で生きてて規範を求められる社会人の中ではかなりまともな部類なんじゃないでしょうか。
とりとめのない話しになりつつありますが、私が良かった!と思ったのは、ヘソンが学生時代も、兵役義務の時も、就職してからも、同じような4人組で楽しく飲んでいる事です。
これは男女とも、同性の友人こそ、気遣い鳴く、変なマウントもせず、目減りしない資産(出典はジェーン・スー スーさんは女性に対しての発言だったかもですが )です。私もそう思います。きっと帰国したヘソンは同じ4人組で楽しく飲んでると思います。
逆に、ノラは最後、なんで泣き出すのでしょうか????これ考えても全然意味わかんないです。
忘れてはいない、信じられない時があるだけ
韓国語を覚えるのは妻の寝言を理解する為
こんな旦那最高じゃないですか、みんなこっちがいいに決まってる。それでも過去のロマンスの、ロマンス味だけ楽しんで、ヘソンには特に感情も、この後の友情もないわけです・・・
友情くらいはあってもよいと思うのですが・・・
PAST LIVES 過去に生きる、だし、縁、でもあるけれど、輪廻転生とか、前世っていうのはなかなか危険な思想ですよ~そんなものは無いけど、一期一会的な縁なら、分かる気がします。
ヘソンはこのNY滞在のそれなりに幸福な、好きな女を訪ねたという思い出だけで、それなりに生きていける気がする。そして、私はそういう男性を、結構知ってる。
2023年5月19日 (金) 09:15
入江喜和著 講談社
初めて読む漫画家さんですけれど、このストーリィというか設定がかなり唸らされました。ここ20年くらい漠然と考えていた事がより鮮明になった感覚があります、まだ考えは完全にはまとまらないのですけれど。
父は闊達で堅気な大工職人、母は専業主婦、姉は女性らしい女性、という家族構成の中で育った妹のゆりあ(主人公)は、姉がねだったバレエ教室に一緒に通いつつも発表会で大役のミルタの配役を得た事で、妬みのような感情に嫌気がさし、バレエからは遠ざかった経験を持ちます。30歳で売れない作家である旦那と結婚、現在は50歳となり、子供なし、義母と夫の3人で夫の実家で暮らす刺繍教室の先生です。というのが冒頭です。
正直、どんな展開になるのか全然読めなかったですが、50歳女性をかなり真正面から主人公と置いた作品って見た事が無かったので、凄く興味を持ちました。
これまでに、映画の世界でも、そして現実でも、いわゆる家族観と言うモノの変化を感じます。少し調べるだけで、専業主婦、という概念も1950年代くらいからですし、少子化とは言っても世界の人口は増え続けていますし、現段階において、うちの国もかなり貧乏になってきています。恐らく、短絡的な金銭を目的とした犯罪は増える傾向にあると思います、残念で怖い事ですけれど。
そういう国の中で、どのような社会でも1番小さな単位である、家族をどう考えたらよいのか?は人それぞれです。今までと同じ1950年代から続く両親と血縁関係にある子供でも良いし、それ以外もあるでしょう。
少子化の問題は根が深いと思うのです、というか必然だと思います。
そもそもなんで核家族化したのか?と言えば、皆がわがままになったから、自由を手に入れたから、です。親との同居を嫌がった、からでしょうし、嫁姑問題をある程度解消するのであれば、世帯を分けるのが得策です。3世代同居する世帯の割合は平成27年の調査で6パーセントを切っていますし、サザエさんの様な家族像は既に1割にも満たない。
さらに、単身者の世帯数は4割を超え、恐らく今後1番多い世帯の形になろうとしています、つまりみんな1人が結局のところ好きなんだと思います。だって、わざわざ『家族』を形成しなくても、外部委託出来るし、生活の重労働な部分は電化出来て久しいです。
しかし、無いものねだりがあるのも人間で、家族がいない人は、家族の幻想を抱いて、リアルを知らずに家族を欲しがり、家族がいる人間は自由を求めて離婚やら別居をするものだと思います。どんな状態でも欲求は尽きる事がありません。
それでも、他者との繋がりはやはり欲しいもの。だから、家族という契約関係まで硬くて重い繋がりではなく、緩やかな関係を、それも血縁という繋がりの無い関係性を求めているのだと思います。それが新しい家族観に繋がっているという感覚が、私の年代でもあります(1970年生まれです)。
また貧乏な国になった事で、家父長的な立場を金銭で賄っていた父親、という像に対して、金銭的な理由でそれを持ちえない人が夫にすらなれない、という自覚もあるでしょう。女性側にもいろいろあるでしょうし、条件がきっと存在するでしょうけれど、ロマンティックラブイデオロギーの強さは、それこそ持てなかった時代だからこそ、自分の娘には、という感覚もあるので、その辺ももう少し調べてみたいですし、本当にいろいろ考えさせられます。
そういった家族の形態の新たな試み、をしている漫画です。
新しい家族像をリアルを持たせるのが難しい。その難しい事を、しかも50歳の女性に持たせる事に成功している漫画だと思います。この人の性格の問題はありますけれど。
そして、凄く大きな問題を、どのように扱えば小さくなるか、という難問に、大きな問題を複数抱えれば、どれも割合小さな問題に見える、という解決方法を実践するのですが、そこにギリギリありうるかも、という細部まで詰めているのが素晴らしい。
しかも直接の中心的な謎を、不在の中心に置き、ここに介護という現実を入れた事で、物語に重みが増しているのも素晴らしい。
なので、風呂敷を広げるまでにはなかなかの謎、というフックと、そこから始まる奇妙なある種の運命共同体を築き上げ、生活を描いたのはかなり凄い事だと思います。
で、ただ、ただなんですけれど、扱っている問題のかなりヘヴィな中に、恋愛要素を入れてくるのが、凄く意外でした・・・割合ここ無くても成立するような気がするんですけれど、多分そうではないんでしょうね。事、恋愛という関係性において、全然男女で違う受け取り方があるんだろうな?と感じました。介護、育児、趣味、仕事、と同じくらいデカい。多分男性は恋愛ではなく性欲として外部委託出来るが、ココだけは出来ないのが女性なのかも。みんながそうじゃないのは理解していますし、男性だって外部委託出来ない人もいらっしゃいますし。
そう言う意味で、いつまで女性なんだろう、とも思うし、それは何時までも続くものなのかも知れません。個人的には生物学的子孫伝達の仕組みは無くなれば楽になれるのでは?とも思う。残念ながら、男性はそれがかなり後にくるので、個人的にはキツイと思うんだけど。でも生物学的子孫伝達だけが目的でもないですから、本当に難しい。
でもここまで真正面から50代の家族像を描いたのは、本当に凄い事だと思います。男性だと割合、というか、ほとんどの作品が、必ずある種魅力的な女性が出てきて、協力してもらってても、ハードボイルドに出来るし、なんならみんなが村上春樹を嫌う、なんで主人公が勝手に女性から好かれるかワカラナイとおっしゃりますけれど、そんなのハードボイルと呼ばれる作品には必ず入ってる要素なんじゃないの?と思います。なので、きっと男女ともに、そう簡単に性別から降りる事が出来ないんでしょうね・・・この辺は女性のおじさん化とか男性のおばさん化とかを考えてみたい、案外いる気がします。
なので、個人的にはばっさり、恋愛要素を切って良かったんじゃないかな?と思います。それでも成立したと思う。だけれど、エモーショナル要素が少なすぎる、という判断があったのか?もしくは現実には無いからこそ、ファンタジー(ハードボイルド作品や村上春樹作品と同じように 都合の良い魅力的な異性)が入ったのかな?という部分が知りたい。
もしくは、恋愛要素の部分を全部カットして、東村アキ子の「タラレバ娘」みたいな今はまだ特異に感じる友人コミュニティにするとか。
男性モノはとかく、孤独を好みがちなんですけれど、それでも、ゆるやかな連帯、ゆるやかな父親の代わりくらいの役割を担う話しがあれば良いのに、といつも思います。
シェアハウス的なアパート(理想は『凪のおいとま』みたいな感じ)の中に、保護すべき対象者(子供がいる家庭、もしくは要介護の方等)が居て、その方々へのバックアップや協力を条件に入居できるような関係性が築けるようなモノがあれば、そして、税制上の有利な点、もしくは居住に関しての何らかの利点があれば、子供や高齢者との繋がりも出来るし、独身の利点も生かせるんだろうけれど、まだなんか良い案があるような気もします。特別養護老人ホームがあるように、一般の人でもそこで何かしらの労力を払えれば、という感じをイメージしますけれど、難しいですよね。信頼関係が無いと。
50代を迎えた人に、オススメ致します。
2018年10月19日 (金) 09:11

ポール・グリーングラス監督 netflix
ラジオの映画紹介で町山さんが強めにオススメしていたので視聴しました。大変ヘヴィーな映画でした、私は全然知らなかった2011年の7月22日ノルウェーでのテロ事件を扱った作品です・・・
ノルウェーのウトヤ島と首都オスロで起こった連続テロ事件の顛末を扱った映画です。単独犯である当時32歳のアンネシュ・ベーリング・ブレイビクは首都オスロの政府庁舎に大量の爆弾を車に積み込んで爆破し、その足でそのままウトヤ島に単独で警官と偽って潜入し、そのまま銃を乱射、当時ウトヤ島には移民政策に積極的なノルウェー労働党青年部の集会が行われており、オルロでの爆発で8名、ウトヤ島での乱射事件では69名の死亡者が出るテロ事件の発生とその裁判を映画化したものです。
単独犯がテロの準備を進める非常に重い映像と、ウトヤ島での生徒たちののどかで爽やかなキャンプ風景が交互に描かれる事で、観客である受け手はこの先に起きる事を実は早く見たいと思わせ、加害者ではないものの、その行為に加担しかねない心理状態に置かれている事はとても上手い編集だと思います。映画化、ですしドキュメンタリーではないので実際の映像では無いんですけれど、早く続きが見たい、どうなるのか知りたい、という欲求の後ろ暗さを実感してしまいました。
主な登場人物は、単独犯ブレイビク、被害者ビリヤル、弁護士リッペスタッド、なんですけれど、とても上手い群像劇でドキュメンタリチックな映画化だと思います。
実際に起こった事件ではありますが、本当のところ、どうだったのか?は私は知りません。しかし映画に近い事実があったのだと思います。非常に重く厳しい現実があります・・・簡単に言葉に出来ませんでした。しかし、それでもなお、考える事を止めるのだけはしたくありません。
ノルウェーで起きたテロ事件について知りたい人、考えてみたい人にオススメ致します。とてもヘヴィーな事件で、現実です。
アテンション・プリーズ!
ココからネタバレありの感想になります。とはいえ現実の事件を映画にしているので、Wikipedia等ネットで調べればすぐに事件の概要は知れます(この事件の概要は ここ です。あくまで私が裏を取ったわけではありません、Wikipediaをある程度信用するとして、という事です)。心地の良い事件じゃありませんからわざわざ知りたくないと感じる人もいらっしゃると思います。けれど、それも個人的には良くない、耳を閉ざす行為だと思っているので、結局いろいろ知れば調べてしまいます。結果的に耳を閉ざし、残虐な事件を遠ざけているつもりで、実は犯人の思いに沿っているように感じるからです。
あくまで個人的な感想です。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
犯人の、独善的で劣等感を暴力でしか解決出来ない上に論理的にも破たんし、もはや精神異常者にしか見えない点は、救いがないです。単純な極右的思想でしか己の貯め込んだ怨念を払拭出来なかったその点に、大変な恐ろしさがあります。自らを怪物として周囲から崇め奉られないと弱い自我が崩壊してしまうほどの脆弱性、排斥主義的な大変簡単なロジックにいつまでも拘泥して、それが醜悪である事を理解していたからこそ、周囲には無害な人間に見えるように行動していた点も、愚かで救いがない事にしか見えないです。他者を見下す事でしか満足が得られない大変小さな男ですが、それがこれだけの事件を起こせた事、その点が非常に気になりました。
政府の、安全保障というテロ対策の粗を指し示すのは簡単でしょうけれど、それだけではない怖さがあって、それはこの犯人が憎んでいる『多様性』の中にこの犯人も含まれる事です。多様性を認めるのであれば事を起こせないようにしながらも、この社会の中でこのような思想というよりもサイコパスな思考の持ち主を許容出来るようにしなければなりません。もちろんテロ行為は大変許しがたい事ですけれど、しかしテロ行為しか表現の手段がない(本当はそうではないんですけれど、まっとうな手段を、思いつく事の出来ない、その道を辿れない早急で粗野な連中)も共生できる社会が多様性のある社会なのであって、矛盾を孕んでいますけれど目指すべき社会だと思います。
誰の言葉かは忘れてしまいましたけれど『貴方の主張には全く同意する事が出来ない。が、貴方が主張する権利は死んでも守る』という事に尽きると思います。
だからこそ、法的に弁護人にはこの愚かな犯人を、法で裁くために、弁護をしなければなりません。この弁護人の役の方は大変味わいのある演技をされていて素晴らしかったですし、脚本演出ともに、言葉で説明しない部分を演技で説明してくれてて素晴らしかったです。被害者から見れば許しがたい犯人であったとしても、報復行動、リンチを認めずに、法の裁きを受けさせるのはとても重要だと思います。しかし、その行為に、犯人を庇うのか?と口汚く罵る輩を出し、子どもの保育園を変えざる得ない状況に追い込まれながらも、淡々と職務をこなし、決して折れない行動は賞賛に値すると思います。
テロでしか自らの尊厳を維持できない人との共生をどのように行うのか?というのは大変困難な命題だと思います。法的に認めなくとも、法外に出てしまう人はいますし、それこそこの映画のテロではなく、現代の日本でも、ヘイトスピーチや排斥主義的な短絡思考を悪びれもせずにデモ行進するような人がいるわけで、この方たちも同じ日本人でこの国で共生していく困難を考えるのと同義だと思います。
また、被害者の中でも特に後遺症と戦うビリヤルのやりきれなさ、無念さ、そしてそこから立ち上がっていく様は大変美しいものがあり、まだ青年のうちに与えられる後遺症としても大変辛いのに、さらに裁判で証言するまでに、戦っていく姿勢が本当にリアルに描かれています。ビリヤルの両親にもそして助かった弟のトリエの存在とその苦悩もリアルに描かれていて良かったです。実のところ本当の意味では変わってあげる事も出来ず、苦しむ両親は、その間にさえ亀裂が入りかかるのも、本当に怖いくらいにリアルでした。何かを克服するのって本当に難しいし、尊い。
弁護士以外にも気になる人物がいて、それが犯人の母親です。この犯人の生育環境は恵まれたものではなかったと思います。しかし生れ落ちる環境や両親を選べた人間はいません。ある種の不平等で理不尽さを含んでいますし、当然でもあります。しかし、不遇な環境が原因ではない事は、その他の恵まれない環境に育った人が何人もいる事で証明できると思います。何故このような人物が出来上がってしまったのか?が気になるわけです。そして私には、この母親の存在が大変重要だと思います。
親になるという事はどういう事なのか?その想像もなく親になっている人が恐ろしいです。果たさねばならない責務のラインというものがあると思います。そのラインを全く気にせずに『親』をやっている人に私は恐怖を覚えます。この犯人の母親もそんな風に見える人物です。なんでも言いくるめられてしまい、放任で甘く、しかし責任を担おうともしません。視野狭窄な考え方をし、単純にそれを信じ込み、その影響が犯人の中にあるように感じました。全く視野狭窄である事に疑問が無いのが恐ろしいです、客観性の無い人の恐ろしさを覚えますし、私の考えも、また別な角度から見れば視野狭窄で浅薄な考えである事もあるのだと思うと、本当に恐ろしくなります。
それでも、この犯人のような人をゼロにするのは大変難しい事だと思います。弁護士が最後の面会で話す言葉の重みを噛みしめています。