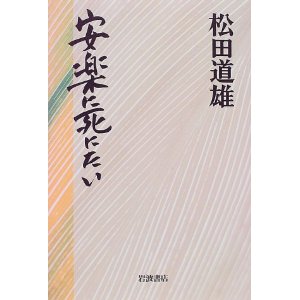
松田 道雄著 岩波書店
患者さんが先生も読んでいただけ、意見を聞かせていただけたら、ということでお借りして読みました。かなりへヴィーな内容ですが、決して避けて通る事の出来ない問題且つ、医療に携わる人間として受け止めなければならない問題です。もっと言えば誰しも生まれてきた以上必ず訪れる『死』をどう捉えるのか?『老い』とは何か?『自己決定権』や『自己と自律』をどう考えるのか?というかなり根源的問いかけに対する今の時点の態度を問われる問題だと思います。この著作そのものは非常に薄くて文字も大きく、僅か数時間で読める内容ではありますけれど、非常に多岐に渡る考えを纏めなければならない示唆を大量に含んだ著作だと思います。
老齢に達した(およそ80代後半くらいと思われます)著者である松田さんが発表したコラムをまとめ、その導入として「はじめに」にひとつひとつのコラムを発表した経緯とアウトラインを解説として添えたものです。著者である松田さんは医師であり、ながらく町の、在野の医師として活躍した方であり、私が著作を読むのは初めての方ですが、小児医療や育児の世界では著名な方のようです。また歴史にも詳しく、医学史にも造詣が深く、裏打ちされた知識から導き出される意見と、実感のこもった実際の老齢者としての情動が相まって文章に説得力があり、面白かったです。そして凄く考えさせられる内容でした。
もの凄く要約すると、必ず死ななければいけないのであるならば、延命治療をして寝たきりの、自由の無い、人の尊厳が無くなるような治療を受けるのではなく、自然に楽に痛くなく死ぬことを、患者の側が選択する自由を認めて欲しい、という著者の考えをまとめ、どうしてそのような考えに至ったのか?を細かく表したものです。医師としての医療者側の視点を持ち、歳を重ね老齢者としての『老い』を実感している人間としての視点をも兼ね備えた松田さんの意見は、一見すると、文字面だけを追うと、過激に見えますが、文脈として読むと理性的であり、非常に切迫感ある訴えだと思います。
誰でも痛く長く苦しむことを望むことはないでしょうし、まして苦痛が長引くことでもその後解決する、未来に希望の持てるものであるならいざ知らずです。延命至上主義であることで見逃されている『キュア(治療)からケア(介護)へ』とよく言われる事でありますし、事実、介護という世界は人間味がなくなってしまうと介護を受ける側も、そして介護をする側にとっても厳しい時間となってしまうでしょう。江戸時代や明治期に於ける臨終の際の状況の日本的な状況と今日の西洋的な病室での臨終とでは意味合いも変わってきているでしょうし、大家族で暮らしていていたために介護者が家族内の(多くの場合)女性であったことと、現在のように核家族化が進んで高齢化社会が訪れた世界では根本的に違っているので特養(特別養護老人ホーム)が出来てきているのも頷けます。もちろん国民皆保険制度の問題点もありましょう、医療従事者としてこの国民皆保険制度の問題点には、全く同意出来ます。
だからこそ、著者である松田先生のような欲求が出てくることは当然と言えます。確かに市民的自由として自分の生死の選択を手に入れたい、という欲求には切迫したものがあります。そして松田先生が市民的自由を手にすることは当然義務や責任が発生する事に言及しているのも好感持ちました。
ですので、私の個人的な意見ではほぼ全てに同意出来ると思います。しかし、しかしです。
おことわり!
今回はかなり重いテーマであります、無理に読まなくても良い問題であるかもしれません。死という忌み嫌われる事を扱っています。が、忌み嫌われようとも絶対確実にすべての人に降りかかる問題であり、逃げられないものでもあります。忌み嫌い考えないのは思考停止であり(もちろん生理的に思考停止であっても普通であるとは考えます)、私は単純に考えておくことに安心を得たいだけなのかもしれません。
なので、非常にネガティブな内容になっております、そんなものをわざわざ読みたくないという方はご遠慮下さい。
また、どうしても本書の内容や結末に触れますので、既読の方は構いませんが、未読の方は内容や結末に触れることも厭わない方であるならお読み下さい。
私はこの現在の終末期医療の問題はいわゆる過渡期の問題と考えます。
確かに江戸や明治期と比して現在の終末期医療が恵まれたものであるとは言い難いですが、西洋の医学治療が導入されて助かった生命の存在を、進歩してきた医学によって生命の質が高まり平均寿命が倍になるくらいになった恵まれた環境を手に入れた事を無かったことには出来ないと思います。また、大家族ならではの家族内葛藤や家族が看取るべきという先入観についても、様々な家族の形を選択できうる(現在大家族が営めないわけではなく、それぞれが核家族を選択した結果の核家族化が進んだわけだと思うのです)現在の方が善き世界であると感じるのです。国民皆保険制度も、もちろん問題点が非常に多いものではありますが、そもそも皆保険制度を持たない(あるいは税金が収入の8割近くを占めるけれど医療費が無料)という世界の大部分の国柄と比べてもそのメリットは大きいと思います、貧富の格差はそれでも日本は少ない方でしょうし、安心して医療を受けられることの利便性や安心感を考慮しないわけには行きません。私は国民皆保険制度を支持します、もっと良くなって欲しいですし、欠点を改良して欲しいですし、正直現場で可能な限りの(例えば、確かに3分診療になりかねない部分を丁寧に、出来うる限り説明と同意が得られるようなインフォームドコンセントを行っていこうと努力している先生方は現在もいっぱいいらっしゃると思います)努力を、時間単価での効率を求めざるを得ないから時間を短くせざるを得ないが、その中での努力をする事が『医は仁術』であることの表出なのではないかと思うのです。現場の人がすぐに法律を変えられないのですから。
様々な問題をこれから解決していく為にも松田先生のご指摘は重要だと思いますが、直ちに解決できる問題ではないのではないか?と思うのです。もっと言うと「老人性疾患」が始まるずっと前からこの問題を個人として受け止めていない限り解決は困難であると思います。
「老人性疾患」が近くに感じられたから急に死に向かっているのではなく、生まれてきている以上いつ死があってもおかしくないと私は思うのです。
生命の重さや尊厳の持ち方は人それぞれだと感じます。もし、老い先短いからこそ自分の生死の選択権を手に入れたいという人がおられても当然と思いますが、同時に様々な立場にも適用されかねない危険も考えに入れなければならないと思うのです。フランスで起こった交通事故で重い障害を負ったヴァンサン・アンベール(詳しくは長くなりますが、高橋昌一郎著「哲学ディベート 倫理を論理する」に詳しいです、私の感想は
こちら)のようなケース、未来があるにしろ全く希望が持てないと自分で判断しているケース、成人しているにも関わらず自身のアイデンティティが確立できていないケース(何らかの宗教的な規制や家庭環境の問題)も考えなくてはいけなくなり、そんなことを言い出せば、何処からが自己を確立できていて、何処からが確立出来ていないか?という線引きそのものが難しいものなのではないか?と思うのです。また誰が判断するのか?とも思うのです。この問題は非常に解決が難しく、何処までを自己の決定に還元するのか?を決めなくてはならないので、それを法律で決められるのか?という疑問が湧きます。つまり単純に自殺を認めるのか?という問題に触らざるを得ないのです。
さらに医療者の自殺幇助の問題があります。罪に問われないためには法律を変えなくてはなりません。
市民的な自由を手に入れ、義務と責任を持ち、自殺を認め、法律を改正し、生死の自己決定権を手に入れ、尊厳の持ち方を各個人が判断して良いことを法的に認めたとしても、難しい問題がまだ2つあるように感じます。
ひとつめは、手を貸すことになる医療従事者の強い負荷のことです。この事を私が強く意識したのはエリック・シーガル著「ドクターズ」という本を読んだから知ったことです。主人公のひとりである医者セス・ラルザスは障害者で意識さえない兄ハウイー・ラルザスを、法を破ってまで苦しまずに安楽死させたいと子供の頃から願い、医者になってついに実際に実行するのですが、その後良心の呵責に苦しめられます。たとえどんな状況であっても、安楽に逝きたいと願う人がいる一方、手助けする側の葛藤を消し去ることはかなり難しいと思います。死刑執行人にさえ罪の意識に苛まれる(ので、せめて罪の意識を薄めるために数人が参加し、誰が直接行ったのかを不明にしておく手段が講じられていると言われています)のですから、医療に携わっている医師が、法的に認められていても、生命を生かす努力をしてきた医師が、その命を閉じる作業に手を貸すのはなかなか難しい問題が残ると思います。もちろん、そういう専門職の必要性が出てきて、精神的ケア等のバックアップがあり、且つ、なり手である医師側にも自主的に参加してくれる方がいれば問題ないですけれど、相当に難しいハードルであろうと思われます。
ふたつめは、当然残される家族の問題です。本人は苦しまずに尊厳を保ちつつ死を受け入れたいと願っても、残される家族が同意出来ないというケースもあると思います。例えば、脳死状態にある家族がいたとして、その家族が温かみの残る本人に触れてしまうと、なかなか脳死を受け入れられない方がいるのと同じ問題です。家族間で長く話し合っているならば多少は敷居が下がるとは思いますけれど、実際その立場にならなければ分からない事、分からない感情が湧いてくることも考えられます。
徒然考えをめぐらせると、今現段階の私の考えとしては、死を選ぶことは難しい、ということであり、また「老人性疾患」を自覚してからでは遅いということ、そして死とはそもそも苦しいものであるのではないか、ということです。
だからこそ、その苦しみを減らす方向の努力は必要ですし、前もって考えを(その方向だけでも)まとめて家族間での同意を得ておく事は必要だと思います。
そしてきっと、死は苦しいものであることを受け入れることが推奨されてきたのではないか?とも思います。死の形も、生の形も、時代に合わせて変化するものであり、生きる時代を選べない以上受け入れるしか無い事柄であるのではないか?と。
ずっといろいろ考えた結論はこんな感じですが、今現在、あの「shall we ダンス?」周防正行監督の最新作が「終の信託」という全く同じ「安楽死」問題を扱っています。正直草刈さんの演技には疑問を持ちますが、観に行こうと思っています。
蛇足ですが少しだけ、気になったのが「憲法」を挙げて基本的人権や尊厳の維持を求めているんですが、私も詳しくはないものの、恐らく「日本国憲法」が規定する先、もっと分かり易く言いますと「憲法」が縛るのは国家権力であって、主権者たる国民ではないと思います。私の記憶では要するに「憲法」は国民の生活や理念を表したものではなく、国家権力があった方が皆がより良い生活が送れるが、その国家権力がまた獰猛なリヴァイアサンなのでそのリヴァイアサンたる国家権力を縛る法律を「憲法」と呼ぼう、と習ったような気がします。いわゆる「立憲主義」の話しですけど。






