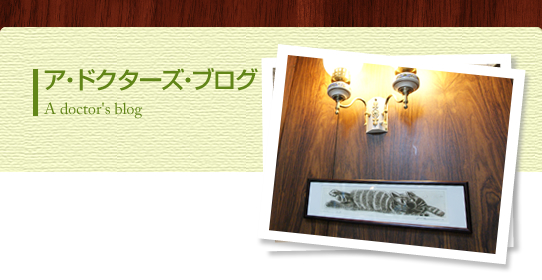新国立バレエ バレエ・コフレ 私は3月16日の最終日に観劇しました。
プログラム
1火の鳥
2正確さによる目眩くスリル
3エチュード
火の鳥 はストラヴィンスキーの曲で振付はミハエル・フォーキン
物語のある演目ですし、非常に筋が分かりやすいバレエ作品。イワン王子が火の鳥を捕まえようとするも、魅入られて火の鳥の羽をもらい受けて逃がす。魔王カスチェイの呪いにより王国が支配された国の王妃からイワン王子は懇願されてカスチェイの呪いを解こうとするも、難しいのですが火の鳥の羽を振り、火の鳥がカスチェイを眠らせる。その隙にイワン王子がカスチェイの大切な魔力の源である卵を壊して平和が訪れる。というストーリィです。
まず、生のオケの音楽の素晴らしさは非常に堪能できました。衣装含む美術も素晴らしかった。
火の鳥の踊り手の踊りが凄く小さく感じます。2mくらいの距離で観ていたら気にならないかも知れませんが、劇場ではどうしても存在感と踊りの小ささが気になってしまいました。主役でもあり、踊りも鳥、それも火の鳥を連想させなければならない非常に重要なキーなのですが、ちょっと残念。鳥を連想させる軽やかさ、俊敏さがもう少しあった方が良かったと思います。ムズカシイ事だとは思いますし、出来ているダンサーが少ないと思いますけれど。既に何度も観ている演目だったり、海外のバレエ団でのDVDなど見てしまっていると、どうしても比較してしまいます。その上で生の素晴らしさを出さなければならないわけで、酷な表現になってしまいましたが、もう少し大きく身体を使って欲しかった。
イワン王子は逆に踊りが少ない分、存在感が必要。観てすぐに王子と分からせなければならないが、異国の話しで、さらに王子となると日本ではとても無理な要求なのかも知れません。それでも、例えば強引さのようなマイムを演出するとか、火の鳥との踊りの際の捕まえている、という部分に王子性のような優雅さみたいな補強が欲しかったです。
いつも思いますが、バレエの本場ではないこの国では、踊りのステップや改訂を行わずに、世界観を補強する演出は必要だと思うのです。ラスト近く、王妃との頬を合わせる挨拶のようなキスシーンのような場面がありますけれど、こういうシーンを恥ずかしがらずに全力で、その気持ちを持って、演じるのではなく行う事が必要なんだと思います。これを日本のどのバレエ団も非常に疎かにしていると思うのです。すぐに改善できるものであり、それだけで世界観を醸し出せるので、恥ずかしがらずにやるべきだと思います。踊りが正確であれば良いというものでは無く、観劇であるわけで雰囲気作りや世界観に没入させる演出は重要だと思いますし、ココで恥ずかしがられると、凄くお遊戯的に見えてしまい残念だと思います。これは海外で公演しないと肌感覚として難しいのかも知れません。新国立バレエは今後海外での公演があるそうなので、そこで批評される事は今後にきっと役立つと思います。
特に日本のバレエの世界は批評があまりに少なく、元ダンサーだけではない批評家を育てるべきだし、そこから気付きや変化に繋げて少しでも一般層への浸透を考えないと難しい状況だと思う。あまりにダンサー向け、経験者向けだけでは広がりようがないとも思ったりします。
それも出来れば面白く伝え批評出来る人が必要。動画配信でも良いので、ウォッカ・ゴリラさんの様な人が増えて欲しいです。
2正確さによる目眩くスリル
音楽はシューベルトで振付はウィリアム・フォーサイス。
男2名女3名の筋の無いバレエ。この5名の中では最初に舞台向かって左手で踊る男性が非常に良かった。ストーリィやキャラクターに頼れない分、まさに踊りですべてを表現しなければならないので、非常にハードルが高いと思います。さらに、タイトな衣装を着ている分、より身体のラインでも説得力が必要になる点で、この後の「エチュード」のように同じ物語の無いバレエの中でも、踊りに焦点が絞られていて、ある種残酷と感じました。何故なら、アジア人である日本人の体形がそもそもバレエに向かない可能性を感じてしまうからです。男性の方がまだダイナミクスを感じやすいけれど、女性の場合はともすると幼児性とか未発達性を感じやすいと思いました。もちろん皆技術は良いのでしょう。そして一定レベルの基準に達しているのでしょうけれど、そういう事とは別に、舞台、生の観劇で映えるか?という点も重要なポイントだと思います。海外のダンサーでのこの演目はまだ観た事が無いので何とも言えない部分はありますけれど。
でも初めての演目、楽しかったです。
3エチュード
音楽はカール・チェルニー/クヌドーゲ・リーサゲル編曲で振付はハラルド・ランダー。
いわゆるバレエのレッスン、ダンサーの練習風景を、その1日を追いかけるような振付。これまたテクニカルな演目。
まず、何と言っても水井駿介さんが素晴らしかったし、この人目当てで観劇しているので、どうしても目がそちらに行ってしまう。牧阿佐美バレエで魅せた「アルルの女」があまりに良かったので、追いかけていますけれど、この人だけが次元の違いを感じさせるバレエでした。
もう1名の男性のソロの方も素晴らしいバレエだと思います、普通なら。中心に居つつ周囲を4名のダンサーで回転する場面も、確かに素晴らしいし拍手が起こるのも理解出来ます。ですが、頑張ってる、が観客に伝わってしまうのはあまり良い事ではないのではないか?と思うのです。安定感と安心感の上に余裕を感じさせ、ギリギリの限界ではなく、余裕を持っているかどうか?は演技の幅に大きな違いを感じさせると思います。
衣装に上腕に膨らみを持たせた衣装、逆に言うとそれ以外はかなりタイトな白一色の衣装なので、どうしてもエレガンスさを出すのに向いているはずですし、それを理解してコーディネートされているはず。それを醸し出していたのは水井さんだけだった・・・と私は思いました。
女性主役のダンサーは、私が読臭として映像でいろいろ観てしまい、ドロテ・ジルベールで観てしまった為に、だと思いますけれど、どうしても、もっと、と言う感じで足りなさを感じました。それは存在感含む空間の使い方や体を大きく使って欲しいという分含めて、とにかく足りない、と感じてしまったのです。身体は絞れていますし、何か技術が足りないとかでもない。だからこそある種残酷だけれど、足りない、と感じてしまったんだと思います。
動画って本当に見比べられる、という恐ろしさがあります。しかし、これはどんな分野でも身体を使う事には通じると思うのですが、間違いなく、動画を使う事でも、ホモサピエンスの身体、技術の習得が早くなり、10年前なら世界でもこの人しか出来なかった、という技術がかなりの人が扱える技術、もちろんプロのある世界でも難しい事もあるでしょうけれど、広がったし早くなっていると思います。
技術が進歩しても、この人だけのオーラとか存在感と言われるものが実際にはあるし、このエチュードで言えば技術的正解はあるのでしょうけれど、それだけではない、魅力のようなものを出せる稀有なダンサーも居て、パトリック・デュポンには確かにあると思います。
水井さんのマズルカの特筆性は、まさにエレガント。そしてこういう事をノーブルというのだと思います。まさに高貴。人をひれ伏させるような圧力ではなく、開かれた、高揚感のあるノーブル。内側から感じさせる踊りを楽しんでいる感覚、技術的に身体的に非常に難しい事をやっているはず、なのに、全く大変さを感じさせない、この動きだからこそ伝わる何かを、そのまま提示出来る強さ、そしてここにアクセント、ちょっとした余裕、音楽的にも余裕があるからこそできる一時停止や急がない動き出し、といったアクセントが効いていると思います。だからこの人だけ妙に浮き上がって見えました。
ルグリに習っていたのは伊達じゃないと思います。
新国立バレエの年齢的な線引きや引退、もしくは椅子の数は全く分からないけれど、もし可能であれば、インタヴューで答えている通り、踊れる機会を増やすのであれば、今のポジションの方が良いのかも知れません。少なくとも新国立をもっと観に行こうと強く思いました。