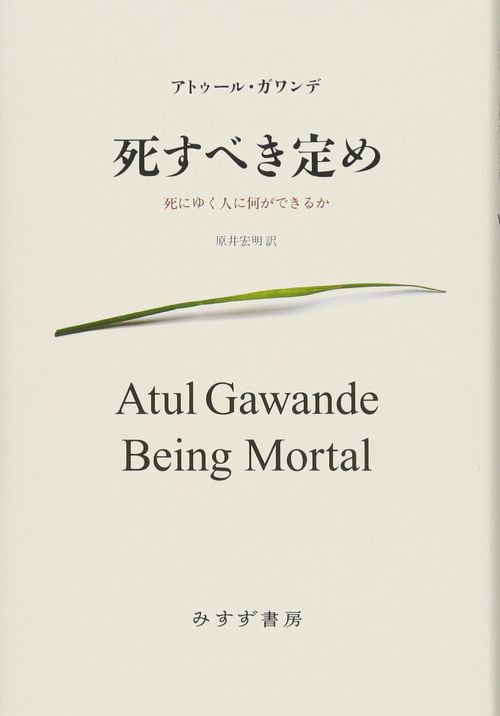
アトゥール・ガワンデ著 原井宏明訳 みすず書房
以前、読書が趣味、と私にも言えた時期がありまして、その時は本屋さんで、いろいろ新刊やら書籍を眺めていてると、時々、あ、これは読まないといけない、という勘が働いく時がありました。今では全くなくなってしまいましたけれど。やはりある程度頻繁に、私の場合ですと、週に2~3冊くらいの、月に8冊くらい読めていれば、またそういった勘のようなモノが働く事もあるとは思いますけれど、今では趣味は映画くらいしかなくなってしまいましたので、そういう事も無くなったのですが、この本は、その感覚の名残のような何かを感じて手に取りました。そもそも、死という事については非常に興味はあるので。必ず誰にでも訪れる、そして何時なのか分からない不安を含む、無になる瞬間でもあり、その前には恐らく苦痛を味わう、という事もよりネガティブに捉えれると思いますし。でも、その事を考えないで生きているのは私には無理というか、どうしても考えてしまう事なので。
医学の発達により、人の命、生命の終着点とされる死が訪れるまでの時間はかなり長くなりました。およそ100年前であれば、平均寿命(とは言え平均寿命は子供の死亡率にかなり影響を受けますので・・・)40歳代であったのですが、これが今は日本では80歳を超えているわけです。単純に2倍になった、と言えます、数字の上では。
さらに、昔であれば自宅で亡くなられていた方の方が圧倒的多数でしたが、最近までは逆転して病院で亡くなられる方が圧倒的に多くなっていました。最近は在宅で死を迎える動きが出てきています。死を取り巻く環境が変わりつつあるという事です。
それでも、どんな人にも等しく、死は訪れますし、1秒ごとに年を取っているわけです。
そんな現代の医療、特に終末期医療の実態を表したのが本書「死すべき定め」です。著者は外科医であり、終末期の医療に疑問を抱いている医療者の1人です。
例えば、肉親が不治の病(とは言え、誰しもが老いという不治の病に罹患しているとも言えると思うのですが)であった場合に、どんな医療処置を選択肢の中に入れるのか?それを決定するのは患者であったとしても、知識や経験が無い患者にどこまでの決定権が与えられるべきか?そしてその肉親とどのように向き合うべきか?といった様々な事の現状、そして、取り組み方や疑問点について、かなり真摯に、エビデンスと経験に裏打ちされた、また著者自身の父親の場合が取り上げられています。
非常に重い話しではありますが、だからこそ必要な事とも思います。その時に、恐らくどんなに準備や心構えがあったとしても、必ず想定していない事や、想定していたとしても実際に、その場に立たされてみないと分からない事があると思うのです。
避けたい不吉な話題の1つであるとは思いますが、だからこそ前もって、ある程度の情報や考え方について、自分でも、家族でも、考えておいた方が良いと思います。だいたいにおいて、全く考えていない事で上手くいった、という事は少ないと思うのです、私の場合ですが。例えそれが不吉な事であったとしても。そして、科学的じゃない、しきたり、とか慣例とかを排除する事は、程度にも、また文化として、とか個別ケースにもよりますが、重要だと思います。今の現代に、盟神探湯で裁判、したくないですよね?同じように、迷信とされるモノにあまり左右されたくない、という気持ちがあります。
日本医師会が進めているACP(アドバンス・ケア・プランニング)もその1つであると思いますし、とても重要だと思いますけれど、そもそも、終末について考えておく、準備しておく、という事を幼少期から訓練しておくのが、最も効果的だと思います。
この書籍は、終末期医療を考える、という事に置いてきっかけとして、そして塾講するにおいて、とても為になる書籍だと感じました。私は自分の死の迎え方に、既にこうであって欲しい、という理想があります。ありますが、この本を読んでさらに改善すべき点や、自身が意思伝達を出来なくなってしまった場合の処断について、考えるようになりました。
終末期を取り巻く歴史的な系譜、そして米国におけるナーシングホーム、そしてアシステッド・リビング施設という理想と現実、最後の日々を迎える上での優先順位や、医療や介護に携わる側としての聞き取り方、家族に対する責任と関係性、そしてビル・トーマス医師という非常に稀有でパワフルな人物を知れた事も素晴らしかったです。
そしてダニエル・カーネマンの「ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?」の中の「ピーク・エンドの法則」を知れた事は、今後の私の日常的な臨床にも役立つと思います。
心に残った文章を少しだけ。
最近亡くなった偉大な哲学者ロナルド・ドゥウォーキンは二つ目のもっと納得の行く自律の概念い気付いた。どのような限界や辛苦にぶつかったとしても、人は自律を保持しようとする――自由である――自分の人生の作者になるためである。これが人間である事の真髄である。ドゥウォーキンが1986年の素晴らしいエッセイに書いたように、「自律の価値は・・・・・・それが生み出す計画の責任にある――自律ゆえに、私たちのそれぞれが明確で連造成のある性格と信念、関心に基づいて自分自身の人生を形作る責任が生じる。自律によって人生に従うのではなく、人生を従えることができ、それゆえ、私たちのそれぞれが、権利の計画によって可能な範囲で、自分が思ったような自分になることができる」。 P136
医師自身が非現実的な見方をしている可能性がある。社会学者のニコラス・クリスタキスによる研究で、五百人弱の末期の患者について、あとどのくらいの余命があるかを主治医に予測させ、実際に経過を確かめた。63%の医師は余命を過剰に見積もっていた。過少に見積もっていたのは17%だけである。余命予測の平均は実際の余命の530%だった。そして医師が患者の事を知れば知るほど、医師の余命予測は外れやすくなった。 P164
1985年、考古学者であり、作家でもあるスティーブン・ジェイ・グールドが素晴らしいエッセイを出した。タイトルは「平均中央値は神のお告げじゃない」である。 中略 「死を甘んじて受け入れる事が、内なる尊厳と等価であるように考える事があるが、ある種の流行になっているように思えます。」1985年のエッセイで彼は書いている。「もちろん伝道の書の教えのごとく、愛する時と死ぬるときがある事に異議を唱えるつもりはなく、実際、混乱の時期が過ぎると私のやり方で、最後の時を穏やかに迎えたいという気持ちも生まれました。しかしながら、やはり死を究極の敵とみなす、より果敢な姿勢をこれからもとりつづけたいと願うとともに、臨終を迎える事に激しく抵抗する人を、責めるべき理由は何もないと思うのです。」 P167
人の死をコントロールできると示唆する見方に対しては私は懐疑的である。今までは本当に死をコントロールした者はいない。人の生の行方を究極的に決定するのは物理学と生物学、偶然である。しかし、私たちに全く希望が無いという訳ではないことも忘れてはならない。勇気とは双方(引用鈴木注 双方とは、老い と 病い)の現実に向き合う強さである。時が経つにつれて人生の幅は狭められていくが、それでも自ら行動し、自分のストーリーを紡ぎ出すスペースは残されている。この事を理解できれば、いくつかはっきりした結論を導き出せる――病者や老人の治療において私たちが犯すもっとも残酷な過ちとは、単なる安全や寿命以上に大切なことが人にはあることを無視してしまうことである――人が自分のストーリーを紡ぐ機会は意味ある人生を続けるために必要不可欠である――誰であっても人生の最終章を書き変えられるチャンスに恵まれるように、今の施設や文化、会話を再構築できる可能性が今の私たちにじゃある。 P243
人の為にも、自分の為にも、読んで良かったといえる良書だと思います。死んでしまうすべての人にオススメ致します。







コメントを残す